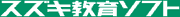GIGAスクール構想が第2期に入り、次期学習指導要領の検討も近々始まろうとする今、「次世代の校務DX」が急がれている。
今までの校務と何が変わるのか。次世代の校務支援システムはどうあるべきなのか。
文部科学省「GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議」で座長を務めた、東京学芸大学教職大学院の堀田龍也教授にお聞きした。
なぜGIGA端末が整備されたか その理念を再確認しよう
今、国は「次世代の校務DX」を推進しています。従来の統合型校務支援システムから、クラウド時代に適した「次世代の校務支援システム」への更新が、求められています。
そもそも、「次世代の校務DX」とは何か。これを理解するには、GIGAスクール構想(以下、GIGA)の理念を改めておさえておく必要があります。
GIGAが始まる前に行われたPISA2018は、日本の子どもたちの深刻な課題を露わにしました。学力は世界上位を維持しているにもかかわらず、「授業でICTを使う時間」が、OECD内でダントツの最下位に沈んだのです(図1)。遊びの道具としては世界でもトップレベルに使っているのに、学習の道具としてはまったく使えていませんでした。

●図1:PISA2018では、授業でICTを利用する時間が日本は最下位に
出典:文部科学省・国立教育政策研究所「OECD 生徒の学習到達度調査2018年調査(PISA2018)のポイント」
画像をクリックすると大きい画像を表示します。
これは単にICTの活用が遅れているとか、学校教育の情報化が遅れているといった問題だけに留まりません。子ども一人ひとりが自分なりの課題を持ち、様々なツールを駆使して課題を解決していくという、自立した学習者になっていないことの現れでもあったのです。事実、コロナ禍の緊急事態宣言で全国一斉臨時休業になった時、「先生が教えてくれないと学べない」という子どもたちが各地で続出し、先生方は頭を抱えました。
このままでは、日本の子どもたちが危うい。何が起きるか、何が正解かさえわからない現代において、自分の人生を自分で切り拓いていく力を育まねばならない。そうした強い危機感が、GIGAを進める大きな原動力になりました。
2018年のTALISも、GIGAを推進する要因になりました。TALISは、OECDが実施している国際教員指導環境調査であり、教員の勤務環境や学習環境について、5年ごとに調査しています。
このTALIS2018で、日本の先生の多忙ぶりが、改めて浮き彫りになりました。特に、事務的な業務の忙しさが著しく、諸外国に比べて倍以上の時間が費やされていることがわかりました(図2)。

●図2:TALIS2018では、校務に多忙な日本の教師の実態が明らかに
出典:文部科学省「OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2018報告書 -学び続ける教員と校長- のポイント」
画像をクリックすると大きい画像を表示します。
日本の先生方は、授業以外の様々な業務も一手に引き受け、子どものために心血を注いできました。その姿は、とても尊いと言えます。しかし、これからは人口が減少していきます。今まで通りの働き方を続けるのは、もう無理です。ICTの力を借りて、効率化できるところは効率化し、先生本来の職務に注力できるようにしなければなりません。また、旧態依然とした働き方をいつまでも続けていては、「ブラックな職場」と見なされ、若者が教員という仕事を選ばなくなってしまいます。事実、教員採用試験の倍率は、全国的に低下傾向が続いています。
だから教員の働き方改革を国は進めているのであり、今回述べる「次世代の校務DX」も、この働き方改革の一環でもあるのです。
こういった背景から、GIGAは実施されました。子どもたちには1人1台端末を与え、学校でも家庭でも学べるようにする。端末とクラウドを使うことで、個別最適な学びと協働的な学びを充実させ、主体的・対話的で深い学びの視点で授業を改善していく。こうした学びを義務教育段階で経験させることで、生涯にわたって学び続ける子どもを育てていく。これが、GIGAの目的です。
教員も、授業や校務でGIGA端末を役立てることが求められています。GIGA端末を用いることで、今まで以上に子ども一人ひとりを正確に見取り、より適切な支援を実現する。従来の一斉授業から、一人ひとりが自分なりに学びを進めていく「複線型」の授業へと変えていく。校務についても、より効率的・効果的な業務を実現し、働き方改革に役立てる。これもGIGAの大切な目的です。
しかし、このGIGAの大切な理念を先生方はどれだけ理解できているのだろうかと、私は懸念しています。
本来GIGAは、4年計画で整備する予定でした。しかし、新型コロナの世界的蔓延を受け、予定を前倒しして1年で整備を完了しました。これは偉業とも言えるのですが、一方で、GIGAの理念を理解しないまま整備を急いだ自治体も続出しました。
たとえば端末にしても、過剰なツールを山盛りに入れ、重くて使いづらくなってしまったり、せっかく便利なクラウドがあるのに、厳しいルールで使用を制限したり。1人1台端末を使って日常的に学ぶというGIGAの本質を理解せず、今までのPC教室と同じ感覚で整備してしまった結果、「GIGA端末は使いづらい」と先生方は不満を感じ、「GIGA端末なんていらない。今まで通りの授業でいい」と背を向け、GIGA端末の利活用も授業改善も進まない。そんな失敗が、各地で起きました。
「セカンドGIGA」に向けて、「次世代の校務DX」に向けて、まずは今一度、GIGAの理念を正確に理解しましょう。現在の環境や活用状況が、GIGAの理念に合致しているか、しっかり見直しましょう。
先生も子どももクラウドを使おう
GIGAは第2期に入っていきますが、このセカンドGIGAでも、標準的なクラウドツールを使って授業改善していくという考え方に、変わりはありません。
GIGA端末のクラウドツールはどれも世界標準のツールですから、学校を卒業して大人になってからも、仕事や学習、生活で使えます。こうした世界標準のクラウドを使った学びを子どものうちから体験させておくのも、GIGAの大切なねらいです。
自治体の裁量で他のツールを追加で整備することがありますが、いろいろなソフトを導入しさえすれば便利になるわけではないことには注意が必要です。それは昔のPC教室時代の価値観です。私たち大人だって、頻繁に使うツールは限られていますし、それで十分事足りていますよね。だから子どもにも、まずは標準的なクラウドツールを積極的に使わせましょう。クラウドを使って、個別最適な学びや協働的な学びを充実させていきましょう。
先生も、授業や校務で積極的にクラウドを使いましょう。先生同士で情報共有や共同編集、他者参照してみましょう。民間企業では、クラウドを使って仕事をするのが、今や当たり前になっています。
子どもも先生も同じ標準的なクラウドを使うのであれば、先生の活用と子どもの活用が、「相似形」になります。わざわざ操作研修を行う手間も省け、導入コストも節約できます。合理的で、シンプルです。
なにより先生がクラウドを使っていけば、「クラウドで何ができるか」「何が便利なのか」という感覚をつかめます。すると授業でも校務でも活用アイデアが生まれ、どんどん使うようになっていきます。この「クラウド感覚」を先生自身が持つことが、とても大切です。
国の調査で明らかになった校務DXの現状と課題
先生が校務でも積極的にGIGA端末を使っていく。これは「次世代の校務DX」でも必要不可欠です。ところが、先生方のGIGA端末の活用が思ったほど進んでいません。昨年、文部科学省が行った、校務DXの進捗状況調査を見てみましょう(図3)。

●図3:文部科学省の調査で、校務DXが進んでいる箇所・遅れている箇所が露わに
出典:文部科学省「GIGAスクール構想の下での校務DX化チェックリスト〜学校・教育委員会の⾃⼰点検結果〜〔確定値〕」
画像をクリックすると大きい画像を表示します。
①教員は校務用の個人メールアドレスが附与されていますか
驚いたことに、「附与されてない」が22%もいます。メールアドレスもなくて、どうやって業務を改善していくのでしょうか?はなはだ疑問です。
②職員間の情報共有や連絡にクラウドサービスを取り入れていますか
⑦教職員が作成した教材等をクラウド上で共有し活用していますか
まだまだ少ないです。もっとクラウドを使ってください。たとえば教材を作るにしても、学年会で共同編集しがら作ったり、過去の教材アーカイブを参考にしたりすれば、より質の高い教材を、短い時間で作れます。
⑤校内研修について、オンデマンド視聴を取り入れていますか
⑥授業研究会や校内研修等での協議にクラウドサービスを用いていますか
取り入れているのが、半分以下になっています。たとえばGIGA先進校では、研修や授業研究会を動画撮影して、チャットに上げています。そして先生は都合の良い時にその動画を見て、チャットでコメントしたり、助言したりしています。
働き方改革が求められる今、先生を一堂に集めて研修したり、授業見学の時間を確保したりするのは、ますます難しくなっていきます。そこをクラウドで行えば、より多くの先生が参加できるようになり、話し合いもしやすく、協議が活発化します。GIGA先進校では、研修や授業研究会に限らず、日々の授業を撮影してチャットにアップし、議論するのが当たり前になっています。たとえば若手が板書の写真をチャットにアップしてアドバイスを求め、ベテランがチャットで助言したりしているのです。
このように、クラウドを使えば先生が日常的に学べるようになります。ぜひやってみてください。
■教員と保護者間の連絡のデジタル化
⑦保護者との日程調整をクラウドサービスを用いて行っていますか
「半分以上している」が、1割に届きません。こういうことこそ、クラウドツールが向いています。GIGA先進校はすぐに取り入れましたし、とても便利で助かっていると喜んでいます。
⑧学校説明会や保護者面談などにオンライン形式を取り入れていますか
「全くしていない」が、実に約7割にも達しています。
先生方だけでなく、保護者もとても多忙です。説明会や面談のために、仕事を休んだり抜け出すのはたいへんなのです。これがオンライン化されると、会社に居ながら仕事の合間に参加したり、自宅で家事の手を休めて参加したりできます。動画なら、気になるところを何度でも見直すことも可能です。「教員にとって便利か」だけでなく、「保護者にとって便利か」という視点で、校務を見直しましょう。
次世代の校務DXで求められるポイント
この調査では、「業務にFAXを使⽤している」学校が、実に約96%にも達しました。校務支援システムが入ってるのに、なぜこんなことになっているのでしょうか?
今は、ペーパーレスの時代です。教科書ですら、デジタルへ移行する時代です。ペーパーレス化とは、単に紙をデジタルに置き換えることではありません。デジタルを前提とした使い方へと進化することを指します。
校務支援システムのあり方も、根本的に見直す必要があります。「次世代の校務DX」では、図のような3つのポイントを挙げています(図4)。

●図4:次世代の校務DXのポイントとは
出典:文部科学省「GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~(1枚概要版)」
画像をクリックすると大きい画像を表示します。
今までの校務支援システムは、クラウドが普及する前に作られたものが多数を占めています。”統合型”校務支援システムという名前が表してるように、ありとあらゆるツールを内包する形で設計されています。「これはクラウドでやった方が便利なのに」と今なら思えるような機能も、統合型校務支援システムの守備範囲になっています。
統合型校務支援システムがあれば、何でもできるようにはなっているのですが、使い勝手が悪い部分がたくさんあります。汎用のクラウドツールでやった方が便利なことは、そのように変えていきましょう。
もちろん、すべてを汎用のクラウドツールで行えと言っているのではありません。子どもの個人情報など機微な情報は、校務支援システムで取り扱います。そして機微度の高くない情報は、汎用のクラウドツールで扱う。こういう使い分けをする時期に入ってきたことを、しっかりと胸に留めてください。
この校務支援システムも、「次世代の校務支援システム」へと変えていかねばなりません。
「次世代の校務支援システム」でまず求められるのは、セキュリティです。学校関係者、教育委員会や行政、外部の専門家など、様々な方がアクセスしやすい利便性と、堅牢なセキュリティを両立させねばなりません。多要素認証や暗号化、ゼロトラストな設計など、最新の技術を用いたシステムであることが求められます。
いくらセキュリティが高くても、外部から隔絶したシステムでは意味がありません。これからは、子ども一人ひとりの様々な情報を連携させて分析し、学校教育に活かしていくことが求められます。たとえば端末の利活用状況などの学習データと、成績や出欠状況などの校務データを統合して可視化・分析して、今後の指導に活かすのです。学級間・学校間、そして行政などの垣根を越えて、必要な情報を共有・連携できるシステムが求められます。
校務支援システムの「ダイエット」も必要です。従来の統合型校務支援システムは、ありとあらゆるツールや機能を盛り込んでいますので、ここから汎用のクラウドツールでもできることは削ぎ落とし、校務支援システム本来の役割に特化した設計へ変えねばなりません。
校務支援システムの設計思想も、「紙ベース」から「デジタルベース」へ変えていくことも求められます。
これまでの統合型校務支援システムの多くは、紙ベースで仕事をする前提で作られていました。たとえば紙の帳票とまったく同じ書式が画面に表示されるため、記入欄を探しながら入力する手間がかかったり、内容を画面上で確認しづらいものもありました。
「画面上で入力しやすいUI」と「印刷した時読みやすいUI」は、違います。紙をそのままデジタル化しただけでは、便利になりません。紙ベース前提の設計から、デジタルベース前提の設計へ変えていかねばなりません。
今までは「紙が主」で「デジタルが従」でした。基本は紙での出力・提出・保管が求められ、場合によってはデジタルでもよい、という考え方でした。この主従関係が、今後は逆転します。メインはデジタルで使って、必要なら紙に印刷してもいい、と変わっていきます。「次世代の校務支援システム」も、この考え方の変化に対応しましょう。
紙を前提としない作りだった「スズキ校務シリーズ」
思えば「スズキ校務シリーズ」は、以前から、そういう作りになっていましたね。たとえば前担任が書いた通知表の所見を、現担任が画面上で確認しやすくなっていたり、若い先生が書いた所見を管理職が画面上でチェックしやすくなっていたりと、紙を前提としない作りになっていました。
高い技術を用いながらも、時代の変化に柔軟に対応し、学校現場の使いやすさを第一に考えて、システムを設計する。こうした作り手側の哲学が今後ますます重要になります。校務支援システムを採用する教育委員会にも、こうした視点が求められるのは、言うまでもありません。GIGAの理念に対応しているか、高い技術力に裏打ちされているか、先生ファーストの設計になっているかなどをしっかり吟味して、導入していきましょう。
ツールを整備するだけでなくルールや意識を変えよう
こうした「ツール」を整備するだけでなく、「ルール」を見直したり、「マインドセット」も変えていかねばなりません。
FAXが未だになくならないのは、「この書類はFAXでやりとりすること」というルールに縛られているからです。ルールを作るのは、教育委員会や管理職です。何かある度にルールを雪だるま式に増やしていった結果、学校現場は窮屈になり、DXの進展を妨げてしまっています。教育委員会や管理職は、クラウドを活用する前提のルールに見直しましょう。
「今まで通りでいい」というマインドセットも変えていきましょう。そのためには、まずは校務でクラウドを使ってみてください。そうすればクラウド感覚がつかめ、便利さを実感し、意識が変わっていきます。逆に言えば、クラウドを使ってみないことには、「今まで通り紙ベースの校務でいい」「今まで通りの授業でいい」となり、意識は変わらないままでしょう。
DXは、一足飛びに実現できるものではありません。まずは紙ベースの校務をデジタル化する「デジタイゼーション」があって、次にクラウド活用を前提に校務や授業を見直す「デジタライゼーション」に進んで、その先に新たな授業や校務のあり方が生まれて高度化していく「デジタルトランスフォーメーション(DX)」へと発展していくのです。
GIGAが第2期に入り、次の学習指導要領の検討も始まろうとしている今、「次世代の校務DX」のために、今できることを今すぐ始め、一歩一歩着実に前進していきましょう。
堀田 龍也
東京学芸大学教職大学院 教授 / 学長特別補佐 博士(工学)
東京都公立小学校教諭から研究の道へ。富山大学教育学部、静岡大学情報学部、東北大学大学院情報科学研究科等を経て、現職。 文部科学省「GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議」座長、「デジタル学習基盤特別委員会」委員長、「リーディングDXスクール事業」事業企画委員長を務めるなど、教育政策の立案に深く関わっている。